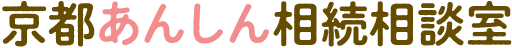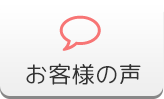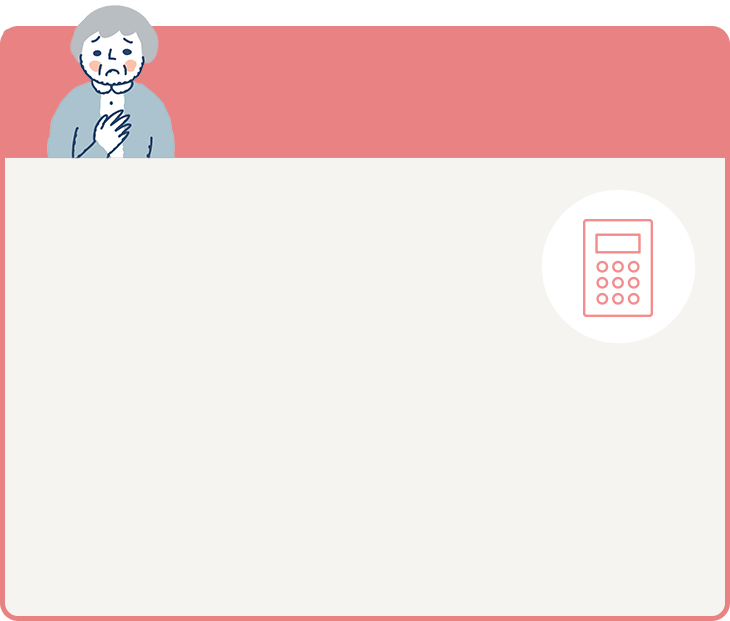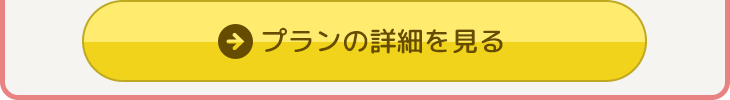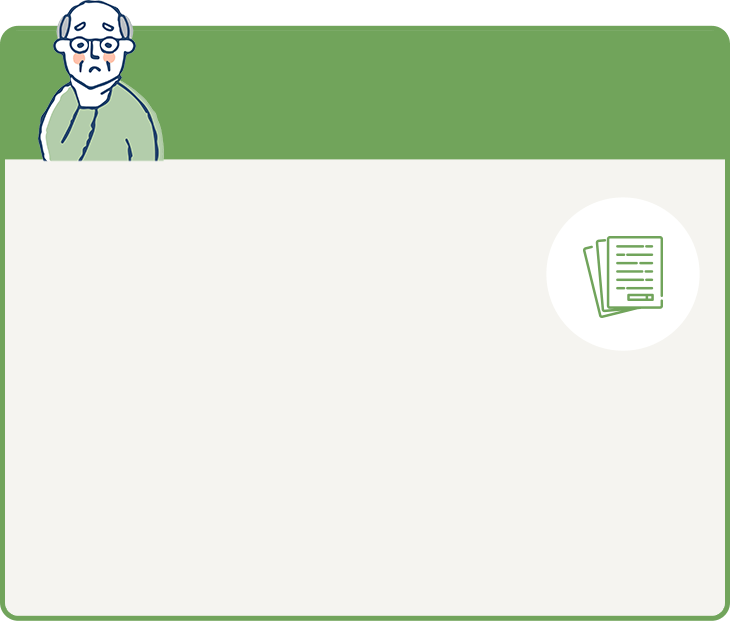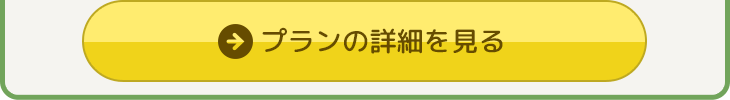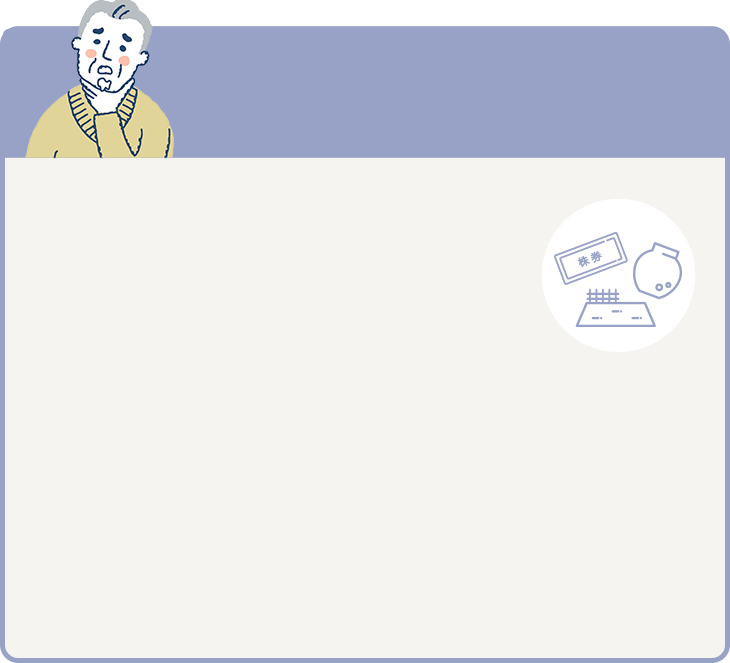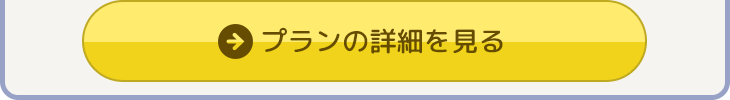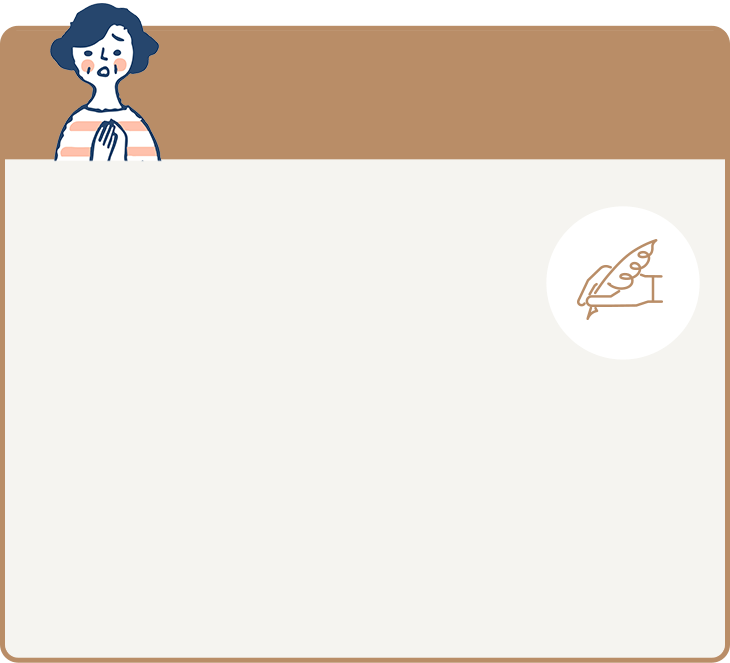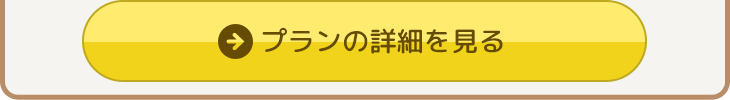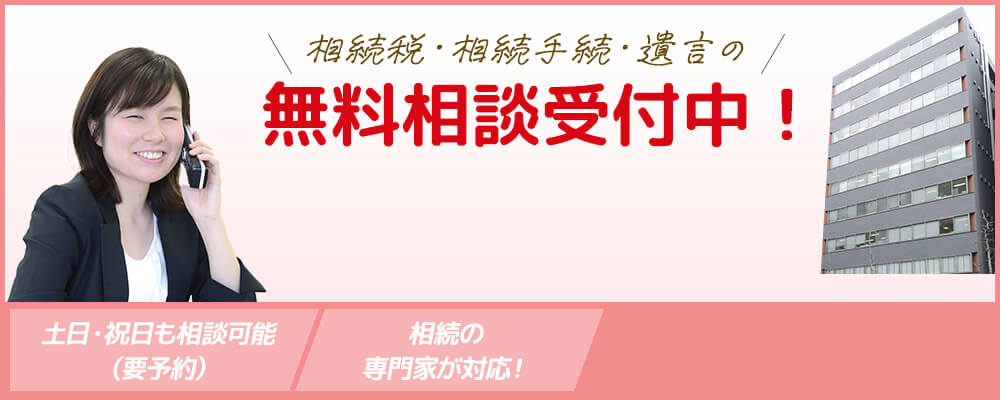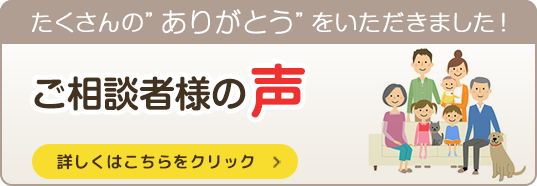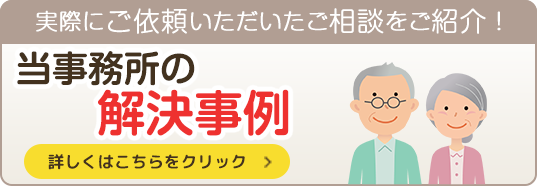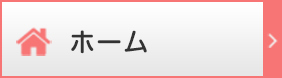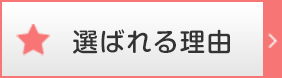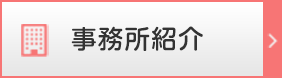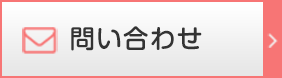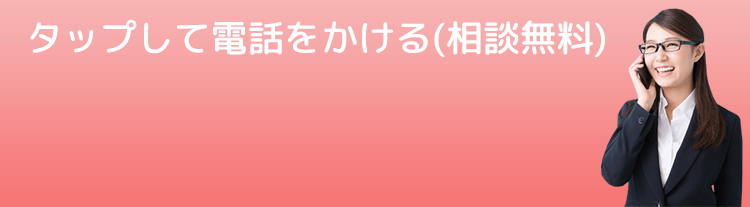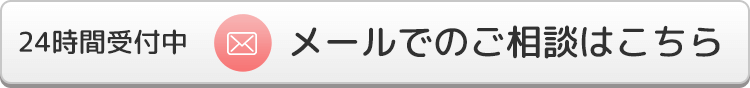【相続税申告】延納と物納
「突然家族が亡くなり、相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そしてそんな場合に、突然多額の相続税の支払いが必要となる。ということも多いでしょう。
このように突然発生した相続税を現金で一度に払えない場合があります。こんな場合で一定の要件をみたした時は、延納や物納が認められます。
延納について
相続税は原則として現金で一時に納付しなければなりません。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
なお、延納により納付する場合には、延納期間中には原則として年1.2%~6.0%の利子税を支払う必要があります。(ただし、公定歩合の変動に応じて、利子税の税率について特例割合が設けられています。) 延納の分割払いの期間は、原則として5年~20年の間で認められます。
次の条件を満たせば延納することができます。
・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・金銭で納付することを困難とする理由があり、延納税額がその納付を困難とする金額の範囲内である場合
・延納税額及び利子税の額に相当する担保が提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
延納の期間や利子税については、相続財産の構成内容、担保として何を提供できるかなどによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に納付した方が、利率が低いという場合もありますので納税方法については十分な検討が必要です。
物納について
延納によっても金銭で納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの現物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというわけではなく、国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
- 相続手続きトータルサポート(相続手続き+相続税申告)
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 相続税の申告書15種類と提出先
- 【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 申告期限が近づいている方へ
- 10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合どんなデメリットがあるの?
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
- 相続税の計算方法
- 相続税の相談は「相続専門の税理士」にすべき理由
- 相続財産とは
- 当相談室が相続税申告に強い理由
- 添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
- 相続税の申告を相続税に強い税理士に依頼するメリットとは?
- 相続税の計算方法は?相続専門の税理士が解説!
- 亡くなった方が現役世代だった方へ
- 【相続税の申告】相続税の計算方法
- 子供名義、孫名義の預金がある方へ
- 【相続税申告】相続税の申告・納付
- 【相続税申告】相続税申告に必要な書類
- 【相続税申告】延納と物納
- 【相続税申告】相続税の期限後申告
- 税務調査のご相談